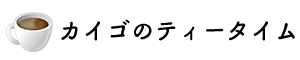こんにちは!
介護施設長の前田裕(Twitter@masakuraudo0415)です。
今回は、家族介護について考えていきたいと思います!
家族介護とは言っても、介護福祉の専門家では無い家族は在宅介護の大変さで疲弊してしまいやすいんです。
そうなると怖い事も起きてしまう事があります。

そういうあってはならない事を未然に防ぐ為にも家族介護の中にも癒しが必ず必要になります。
そこで、レスパイトケアが今再注目されています!
在宅介護の要でもある「ケアマネジャー」がどれだけ頑張っていても、現実問題として「地域包括支援センター」へも相談へ行けず、家族介護に疲れ果ててしまい最悪な結果を辿る方が多くいらっしゃいます。
恐らく、介護士や介護福祉士・ケアマネは「なんで早く相談しないの?」
と考えるかも知れません。
この「家族介護」については、とてもデリケートな内容が多く介護する家族は「使命感」を抱えてしまい、気付いた頃には「もう限界です」と言う感じになっている事が多いんです。
こんな、非常な事が核家族化が増えている現代社会に置いても起きているんですね!
そんな中で、活躍するのが居宅ケアマネジャーや地域包括支援センターです。
もっと身近に言えば、民生委員さんや自治会の方々です。
在宅介護をしている家族さんが唯一相談できる存在の代表格です。
しかしです。
更に根深い問題もあります。
それが、「家族の方が世間に知られたくない」「何とか自分で出来る事は介護する」
と言う日本人独特の、文化が未だに強く根付いているんですよ。
これが、これからも顕著化していくのは解りきった事です。
なので、地域包括支援センターも自治会や民生委員さんと常日頃から連携しています。
しかし、それでも頑張りすぎている家族介護の実態の把握は難しいのが現状です。
そんな、家族介護を何とかする為に、介護従事者や居宅ケアマネジャーも積極的なレスパイトケアを考えていければと思います。
それでは、今回もよろしくお願い致します!
レスパイトケアとは何なのか?

レスパイトケアをご存知の方も多いかと思いますが、改めて一緒に考えていきましょう!
そもそも「レスパイト」とは何なのか?
レスパイト(Respite)とは、「小休止」を意味します。
なので、正確に言うと「レスパイトとケア」という感じで分けて言う事もあります。
「小休止の支援」ですね。
(但し、小休止にも大なり小なりありますからね!)
介護にあたる方々が一時的に、公的機関や介護サービスを受ける事で、「小休止」や場合によっては長期的なレスパイトケアを行う事もあります。

どれだけの在宅介護を主介護者が行なっており、特に「休む余裕・癒しはあるのか?」と考える所からの思考が基本です。
レスパイトケアの代表的な介護保険サービスとは?

レスパイトケアを考える際には様々な手段がありますが、今回は介護保険サービスを利用して、家族介護の負担を減らす事に注目していきたいと思います!
レスパイトケアで良く利用される、代表的な介護保険サービスについて
・短期入所生活・療養介護(通称ショートステイ)
・通所系サービス(通所介護・通所リハビリテーション介護等)
・訪問介護(ヘルパー)
この3つの介護保険サービスがメインだと思います。
在宅介護で主に利用されるところです。
特に注目したいのが、ショートステイですね!
ここはレスパイトケアの代表的な存在です。

他にも、日中は家事もあるから介護までは手が回らなくて、休まる暇も無い。
と言う方には通所系サービスや、一緒に住んでは居ないが高齢者夫婦の生活・身体介護をお願いする場合に訪問介護(ヘルパー)を利用する事が可能です。
ここで重要なのがケアマネジャーが積極的にレスパイトケアを熟知し、マネジメント出来ているかが問われます!
そして、周りの在宅介護支援を行なっているインフォーマル・フォーマルサービスの介護復職の方々はケアマネへ情報提供をしっかりしていくことが大切です。
介護福祉のプロとして頑張りましょうね!
そして主介護者は、既に疲れ果てているかもしれませんよ?
そこに気付けているか?
重要なポイントですね。
ただ、この辺りは「すでに頼っている」と言う方も多いはずです!
しかし、これらを知らない「介護保険制度利用の申請」自体をしていない家族の方々も多いので、是非「地域包括支援センター」へ相談してみましょう!
介護保険制度を知らない家族介護をしている家庭を助ける事が大切
中には、「介護保険制度を利用したく無い」又は「介護保険制度を利用できない」と言う家庭も実は多く存在します。
特に、貧困世帯です。
(ここが特に重要です)
例えば、生活保護受給者へは、行政がしっかり介入してくれるのでレスパイトケアはしっかりと構築されています。

(又は、介護保険料を納めていなかったら介護保険サービスをまともに受けれません)
この様な、貧困世帯へのレスパイトケアが今後増加していくでしょう。
そこをどう助けるかは、「地域の誰かが気付く」「友人が気付く」
しか手段がありません。
地域包括支援センターが、どうにか介入出来れば良いんですが・・・
基本的に、そう言う「貧困世帯」はなかなか表面化されない(意図的に隠す)ので、介入するまでに時間が掛かる事が多いです!
これでは、そんな家庭を介護する主介護者である方は全くの癒しが無い状況が365日続く訳です。
そこを気付くには?又は、助けるにはどうするべきか?
隠れ家族介護貧困世帯を救う事が出来る鍵は大家さん!
え!?大家さん?
そう感じたかと思います。
そうです、隠れ介護貧困世帯家族の多くは「古くて家賃が安いアパート」に住んでいる事が多いんですよね。
(馬鹿にしている訳ではありません)
そこで、活躍するのが大家さんです!
大家さんへ毎月、基本手渡しで家賃を支払っている訳ですから。
その時に、支払っている方は高齢者世帯か主介護者なんです!
そこで、大家さんなら住んでいる環境や金銭的な滞りがあった場合に、「何が起きているの?」
と考える訳です。
ここまでくると、答えは簡単です。

又は、そう言う物件の情報を個人情報を守り、探っていきましょう。
大家さんへ話を聞いていく事も大切です。
大家さんは、部屋の鍵だけ持っていないんですよ。
基本的に貧困高齢者世帯は、自治会への支払いも出来無い場合が多いので、見つけるのが難しいんですね!
その裏に、家族介護で疲れ果てたレスパイトケアが直ぐに必要とされる方々が隠れているんです。
ここまでのまとめ・・・

レスパイトケアは、ケアマネと利用者さん・家族の関係性の構築がとても重要です。
そこまで、出来ない事情があるならば、管理者や地域包括支援センターへ相談しましょう!
何でもかんでも、ケアマネジャーが1人で考える事は意味がありません。
ケアマネにもレスパイト(小休止)は必要です。

どんな「人」でも、癒しの時間がないと「仕事や家事」は出来ないんです。
そんな、精神状態をコントロールするのにも人それぞれに限界値があります。
これは、とても大切な介護福祉の考え方です。
そこで、介護支援専門員には先ず、レスパイトケアを学んだが良いと感じます。
介護支援専門員実務者研修で、レスパイトケアは大きく学ぶ事は今の所ありません。
ケアマネジャーは、結構精神的にキツイ職業なんですけどね。
もっと、レスパイトケアについての内容を組み込んで欲しいと願うばかりです。
ケアマネジャーも精神的なコントロールは大切ですね!
社会福祉士も同じような事が言えますのでレスパイトケアを知る大切さは無限大なんですよね。
なので、ケアマネジャー自身がレスパイトについて知る事で、利用者さん家族への本当の「レスパイトケア」が出来るはずですから。
又、隠れ貧困高齢者世帯への主介護者へのレスパイトケアが出来るまでの構築は、早急に動いたが良いでしょう!
地域包括支援センターの腕の見せ所ですね!
こちらの記事もご参照下さい。
地域包括支援センターの役割や社会福祉士についての内容です。
それでは、ここまで読んで頂きありがとう御座いました!
以下にも、様々な情報を掲載しておりますので読んで頂けると嬉しいです。