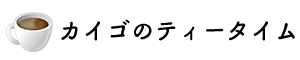こんにちは!
介護施設長の前田裕(@masakuraudo0415)です。
スピーチロックは「虐待」と教わることは多いと思いますが、どこまでがスピーチロックにあたるのでしょうか?
虐待に至る前に拘束があるんですが、その辺りもお伝えしていきたいと思います。
そして「ちょっと待って」など普段使っている言葉も虐待と取られることもあります。
「いやいや、そんなの虐待だったらどうしようもないよ!」と介護現場では考えますよね!
この記事では、どのような表現がスピーチロックにあたるかをまとめています。
スピーチロックは判断が難しい
スピーチロックは「虐待」の一種と言われていますが、他のフィジカルロック、ドラッグロックに比べて判断が難しいと言われています。

少し待っていて欲しい時に「ちょっと待って」などと言ったりすることがありますが、これも患者さんや言い方によっては「動くなと言われた」のように解釈されることもあります。
だからといって、全てを気にしていては何も患者さんと話せなくなってしまうので仕事になりません。ここがスピーチロックの難しいと言われる所です。
スピーチロックの事例・具体例
実際に現場のスピーチロックの問題を改善させるために悩んだ女性の意見です。
「介護現場で働いていました。身体拘束というとひもで椅子に縛りつける、部屋に鍵をかけるなどを想定しがちですが、『それは食べないで!』『立ち上がらないで!』など言葉での拘束(スピーチロック)も拘束になります。
物理的な拘束は私の職場では見かけませんでしたが、言葉の拘束は見逃されていました。最近はサービス向上のため、スピーチロックをしないための研修が行われているそうです。
いわゆる危険行為も、少しの言葉掛け、介護者の対応などで改善されることが多い。体感したこともあります。しかし職員不足が叫ばれる現状、そこまで手が回らないのも事実です。本人の安全をとるか、尊厳をとるか、いまだに悩み続けますし、答えは出ません」
(神奈川県・20代女性)
スピーチロックと考えられる言葉
スピーチロックに該当するとしてよく挙げられる言葉です。
「しないでください」
「動かないで」
「しちゃだめ」
「なんでそんなことするの」
「立たないで」
「ちょっと待って」
「また〜ですか → またトイレですか?」
「ちょっと待って」などは反射的に言ってしまいがちです。こういった、反射的に言ってしまいそうな言葉も含まれるのがスピーチロックの難しい所です。

ただ、そんな声かけも使い方に工夫をすることで虐待や言葉の拘束にはならないんです。
更に深掘りしていきたいと思いますね!
どんな時によく発言されるのか
こういう発言は『介護の現場がバタバタしている時』『利用者・入所者さんが身体的・精神的に重度の方であまり動き回ってほしくない時』に焦って言ってしまう時に出やすいです。
仕事が少なくて介護士・看護師も心に余裕がある時には、そこまで問題にはなりません。
人間、焦っている時ほどスピーチロックになりやすいのが特徴です。
介護職員は常に冷静に様々な状況判断が大切だと言うことです。
スピーチロックの対策
最近は介護の現場での「虐待」がニュースに取り上げられたりと悪い意味で話題になりやすいです。
その為それぞれの現場がスピーチロックにきちんと対策できるよう勉強会やマニュアル、研修を実施しているところもあります。
それだけ、スピーチロックが問題視されていると言うことなんですよ。
スピーチロックについての知識は介護職には必須な事項だと言うことですね!
身体的な虐待ばかりがニュースになりますが、言葉での虐待であるスピーチロックをよく知ることは大切なことなんです。
マニュアルや勉強会を準備しているところも
マニュアルや勉強会を独自で行っていたり、フォーラムみたいなところで行っていたりします。
内容は「スピーチロックとは?」というところから始まったり、実際の具体的な対策や言葉のかけ方まで触れたりとさまざまです。
そこで以下にスピーチロックにならない声かけの言い換えをご紹介しますので合わせてご参照下さい。
まとめ
いかがでしたか?スピーチロックは意外と普段使う言葉の中にも含まれています。
スピーチロックは普段使うような言葉も該当する。
仕事で忙しい時、高齢者さんが重体で焦ってしまう時に言ってしまいがち。
言い換えなどを勉強し、各々が対策する必要がある。
看護や介護など、介護・医療現場に携わるものとして「そんなこと言われても困る」と言わずに、気を遣っていきたいですね。
「スピーチロック」のまとめ記事
スピーチロックに関するまとめ記事を作りました。
スピーチロックに関して調べたい情報はこちらの記事から手に入ると思いますので、是非読んでみて下さい。
また、スピーチロックに関する研修等で参考にして頂いて構いません。
大切なことは「ちょっと待ってて!」の前に理由を簡潔に付け加えることです!
いきなりスピーチロックが完璧に出来るわけでは無いので、頭に入れつつ実践あるのみですね。
ここまで読んで頂きありがとう御座いました!
以下にも様々な情報を掲載しておりますので読んで頂けると励みになります。